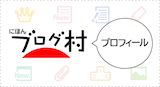おすすめ!初めてのカートリッジ交換【オルトフォンのヘッドシェル付き】がお得!
初めてのレコードプレーヤーなら【ヘッドシェル付きカートリッジ】を選んで交換してみよう!
初めて私が購入したレコードプレーヤーTEAC アナログターンテーブル TN-3Bには、オーディオテクニカのVM型カートリッジ VM型ステレオカートリッジ AT-VM95Eが付属されている。
今回新たに購入したのは、ヘッドシェル付きのMM型カートリッジでオルトフォンからでている2MRED。
この2MREDに最適なヘッドシェルを組み合わせて1000本限定で発売されていた。
1000本限定生産モデル】ortofon 2MREDSH4R (MMカートリッジ+専用レッドカラーシェルセット) オルトフォン 2MRED
オーディオテクニカと同様に、オルトフォンのMM型カートリッジ2MREDは比較的リーズナブルだが高音質なレコードプレーヤーの付属カートリッジとしてよく登場する。
とても信頼性の高いカートリッジMM型カートリッジだ。
【もくじ】
- おすすめ!初めてのカートリッジ交換【オルトフォンのヘッドシェル付き】がお得!
- 【初心者におすすめ!カートリッジの選び方の4ポイント】
- カートリッジの交換手順(ちょっとしたコツをご紹介)
- オルトフォンのMM型カートリッジ 2MRedのファースト・インプレッション
【初心者におすすめ!カートリッジの選び方の4ポイント】
1.初めからカートリッジが専用のヘッドシェルに取り付けられていること
2.MMカートリッジであること
3. 軽量であること
4.自分の好きなブランドや信頼のあるメーカーから選ぶこと
1.カートリッジがヘッドシェル付きがおすすめな理由は?
初心者にとって、アナログレコードのカートリッジの交換をするといっても、何をどうやっていいの分からない事が多い。
今回、オーディオ歴30年だか初めてレコードプレーヤーを導入した私が、初めてのカートリッジの交換に挑戦してみた。
手始めということで、初めからヘッドシェルにカートリッジが取り付けられているものをチョイスした。
その理由は、TEACのレコードプレーヤーに付属しているヘッドシェルにどんなカートリッジが取り付け可能か分からないためで、もし購入したカートリッジが既存のヘッドシェルと相性が悪い場合に調整に苦労する可能性があるからだ。
最初のうちはヘッドシェルとカートリッジがセットのものが無難
2.MMカートリッジから選ぶ理由とは?
カートリッジには、メジャーなところで言うと大きく分けてMM型、MC型という2種類のものがある。
今回購入したTEACのレコードプレーヤーにはオーディオテクニカのAT-VM95EというVM型というカートリッジが取り付けられていたが、これもMM型の仲間であると考えていい。
AT-VM95Eのヘッドシェル付きが発売されている。
すでにオルトフォンの2MREDあたりを持っているのなら、同じくコストパフォーマンスの高いオーディオテクニカのVM型の音と比較するのも楽しい。
MM型を選ぶ理由としては、MC型よりも価格が安いものが多いのもあるが、針が折れたときに自分で針を交換できることがメリットとしてある。
また、AT-VM95シリーズには、針を無垢マイクロリニア針の95MLやシバタ針の95SHなどカートリッジ本体と互換性のある別の種類の針に交換ができる。
針によって音が全く異なってくるので非常に楽しい。
オルトフォンの2MRedも、2MBlueの交換針と互換性がある。
ちなみに、MC型カートリッジでは、針の交換が自分ではできないためメーカーに修理に出す必要がある。
MC型カートリッジで超定番のDNONON DL103の修理費は結構高い
プリメインアンプにPHONO端子があるもの多くはMM型に対応しており、中にはMC型に非対応のものも存在する。
又、音源のデジタル化(CDやPC、ネットワークプレーヤー)に伴い、プリメインアンプにPHONO端子がそもそも装備されていない事がある。
最近のレコードプレーヤーは、レコードプレーヤー本体にフォノイコライザーが内蔵されているものが発売されており、プリメインアンプにPHONE端子がなくても、AUX端子(CD端子やTUNER端子でも良い。)に繋いでレコードが再生できるようになっている。
そのようなレコードプレーヤーは殆どがMM型(VM型も含む)のカートリッジしか対応していないためだ。
3. カートリッジが軽量である理由
レコードプレーヤーのトーンアームによっては、重量級のカートリッジが水平のゼロバランス良が取れなくなる場合がある。
軽量級のカートリッジのほうが多くのトーンアームに適合するため無難である。
4.好きなブランドを選ぶ(信頼の高いメーカー)

私の個人的な事だが、長い間オーディオを趣味としてきて未だかつてオルトフォンという有名なオーディオメーカーの製品を所有したことがなかった。
この機会にオルトフォンを試してみたいという、オーディオ好きの無邪気な気持ちからである。
別にヘッドシェル付きのカートリッジは、他のメーカーからも発売されているので上記1.2.3の条件から自分の好きなブランドを選ぶと良い。
オルトフォンとオーディオテクニカから選べば間違いない。
カートリッジの交換手順(ちょっとしたコツをご紹介)
以下、実際にオルトフォンのカートリッジに交換した手順を記す。
簡単だがイメージだけでも掴んで貰えればと思う。
*注意:必ずレコードプレーヤーもプリメインアンプも電源はOFFにしておくこと。
①カートリッジのオーバーハング調整を行う。
いきなり小難しいことから始めるが、オーバーハングについては前回の記事で説明しているので必ず参照してほしい。
👇オーバーハングについての記事
オーバーハングの意味を理解したという前提で続きの手順に移る。
①−1 新しく取り付けるヘッドシェル付きカートリッジの取り付けネジを少しだけ緩める。

①−2 ヘッドシェルの付け根から針先までの距離を適正な長さになるよう調整する。

メジャーやモノサシでも良いが、細かく計測する必要があるので、予めタコ糸などに印をいれて適正距離を作っておくと非常に楽に調整できる。

針のカバーを外して針先とヘッドシェルの付け根(ゴムパッキンの手前のところ)までの距離を計る際に、硬いメジャーやモノサシで針を傷つけたり破損したりする恐れがあるので、タコ糸などを使うと安全かつ正確に調整しやすくなるのでお勧めだ!





長さの調整だけでなく、ヘッドシェルにカートリッジをまっすぐ取り付けることも重要ポイントである。
問題なけれな、ネジを増し締めしてカートリッジをしっかりと固定する事。

②既設のカートリッジをヘッドシェルごとトーンアームから取り外す。
トーンアームとの接合部を回して取り外す。

もし既存のカートリッジの針が曲がっていない場合は、針先とヘッドシェルの長さが同じになっているか念のため新しいカートリッジと見比べてみると良い。


③オーバーハング調整済み(手順①)の新しいカートリッジをトーンアーム取り付ける。

④トーンアームのバランス調整や針圧調整をする。
各自のレコードプレーヤーの取説をみながら手順を追って行う事。
なお、針圧に関しては、カートリッジ毎に適正な針圧があるのでカートリッジの取説やカタログ、ネットなどで仕様を確認すると良い。
ちなみに今回のオルトフォンは取扱説明書が英語だったので、インターネットでカートリッジの仕様を調べて、1.8gが適正な針圧と知った。

以上で取り付け完了だが、最初はボリュームを絞り気味に小さな音量で再生してみて様子をみてから問題がなければ通常音量で再生するとよい。
もし、今まで再生できていたレコードで、音飛びや大きな歪が出る場合はどこかがおかしいので、手順①から④を再確認していく事。
オルトフォンのMM型カートリッジ 2MRedのファースト・インプレッション
第一印象は、レコードプレーヤーに付属していたオーディオテックニカのカートリッジよりもオルトフォンは音がカチッとしている印象を受けた。
とくに女性ボーカルやサックス、クラリネットなど中高音が耳の奥に押し込まれるような感じがしたが、特に私は大音量で聴くことが多いためそのような印象になったかも知れない。
逆に言えば音量を絞ってもボーカルなどがハッキリと聴き取れる。
しかし、オルトフォンのカートリッジを取り付けてわずか1日目である。
オーディオテクニカのカートリッジのときも最初は寝ぼけた音がしていたが、振動対策や3連休のときに1日8時間くらい鳴らしているとかなり高音質になってきたという体験がある。

オーディオ機器やケーブルなどは、エージングで大化けすることも珍しくないので、しばらくオルトフォンのカートリッジを鳴らし込んで様子を見たいと思う。
また、カートリッジは取り付けネジやワッシャー交換などで、音質が変わるらしいので、そのうち試してみたいと思っている。
もし初めてカートリッジを交換するのなら、ヘッドシェル付きのMM型もしくはVM型でヘッドシェル付きを選ぶと、カートリッジがどのようにヘッドシェルについているか?などが理解しやすく、今後の発展性もあるのでお勧めしておく。
今後、カートリッジの交換や調整に慣れてきたのなら、ヘッドシェルとカートリッジ本体を繋ぐシェルリード線の交換をすると、かなり音が変わるのでぜひチャレンジしてみていただければと思う。
✅カートリッジの使いこなしのほかにも高音質再生の手法を記事にまとめています。
👇もっとレコードを高音質で聴きたい方はこちら👇
👇もくじをタップすると読み返したい箇所にジャンプします。
【もくじ】
- おすすめ!初めてのカートリッジ交換【オルトフォンのヘッドシェル付き】がお得!
- 【初心者におすすめ!カートリッジの選び方の4ポイント】
- カートリッジの交換手順(ちょっとしたコツをご紹介)
- オルトフォンのMM型カートリッジ 2MRedのファースト・インプレッション
2021年10月4日
2020年3月17日