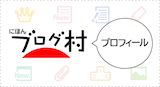スピーカーの吸音材は自然素材で適量適所がいい
スピーカーの調整のひとつとして吸音材の交換をする方法がある。
吸音材はスピーカーユニットの裏側の余分な音を吸い取ったり、エンクロージャーの中の空気ばねの係数を変えて低音の出方を調整したりする役割がある。
吸音材は音のエネルギーを熱に変換することによって機能を果たしている。
すべての周波数を吸収しているわけでもなく、反射したり、吸収せずに透過してしまったりもする。
吸音材はその量や貼る箇所や素材によって変わってくるので、カット・アンド・トライ(トライ・アンド・エラー)を繰り返して自分好みに調整するしかない。
誰もその人の正解は知らないし教えてくれないのである。
そんな中、この記事が少しでもヒントや参考となれば幸いたど思う。

古くから吸音材はグラスウールや粗毛フェルトやエステル素材などいろいろなものが使用されている。
今回は当方の自作スピーカー10cmバックロードホーンのスーパースワンを使って、
ウール吸音材 DCP-A001を試してみた。
結論からいうとかなり好感触!
特にスーパースワンのヘッド部分に厚みがちょうどよく、小型のエンクロージャーや細かい部分貼りをする場合にウール吸音材 DCP-A001は非常におすすめできる。
(※スーパースワンについてはこの記事の後半に記載している。)
【もくじ】
スピーカーの吸音材を交換する
やっと本題だが、吸音材については、粗毛フェルトや脱脂綿、ミクロンウール、
ウレタンスポンジ、さらに吸音材をブチルゴムテープで貼り付けるなどあらゆる事をやってきた。
これはやりだすとキリが無く正解も無い。それぞれの部屋や装置などの環境や音楽によって左右される。
スーパースワン を塗装したら何倍も音質が良くなったので、しばらく満足していた。
しかしこの間の記事に書いたが、スーパースワン の胴体のデッドスペースに砂利から鉛粒とジルコンサンドに入れかえて音質が良くなったので、次はユニットにブチルゴムで対策した。
その時、吸音材が気になった。
ユニットを外すと中は、過去に幾度となく吸音材を接着したボンドやブチルゴムゴムの跡で相当汚い。(閲覧注意?)

内部の塗装も考えたが、どう考えても作業が上手くいくと思えない。
PARC Audio のウール吸音材に変えてみる
以前から気になっていたのがウール吸音材 DCP-A001だ。

なにやら説明にも良さそうな事が書いてある。
そう高いものでも無いので早速発注した。
届いたものを見るといかにも天然素材で真っ白に漂白されたものではなく、
自然な色合いだ。

今まで市販の吸音材は、スーパースワン のような小型の箱に入れるには分厚くて自分で割いて適当な厚みにして使っていたが、均一な厚みにはならないため、かなり適当だった。

今回の吸音材は薄く使い勝手が良さそうだ。
◆早速ウール吸音材 DCP-A001をハサミで切り、スーパースワン のユニットを外しユニットの背面の奥に一枚貼り付けた。



ユニットを取り付け、音を出した瞬間ノラジョーンズのボーカルが耳をつん裂く!
◆直ぐにまたユニットを外し、今度は側面の片面にもう一枚貼り付けた。

大体スピーカーの吸音材はユニットの後ろか対向面の片側に貼るのが基本なのでそれを試してみた。
またユニットを取り付け曲を流す。
さっきよりノラジョーンズのボーカルもマシになり、ほかのアーティストの曲も聴いたが、確かに低音域など今まで聴き取れていなかった音に気づかされる。
しかし、何か面白くない。
バックロードホーンのインパクトのある押し出しの強さが薄れているし、左右のスピーカーとの繋がりもあまり良くない。
これは、過去に何度か経験しているが、私のスーパースワンの場合だけかもしれないが、空気室いわゆるユニットが入っている箱の側面に吸音材を貼ってもあまり良い結果になった事が無い。(あくまでも私の場合)
今までも何度も、側面に貼っては剥がしの繰り返しで、結局剥がしている。
◆そこで、ユニットの後ろに貼った吸音材の上から、もう1枚重ねて2重貼りにしてみた。

ユニットを取り付け、同じ曲を聴く。
これは良かった!低音も深くなり、左右の音場の繋がりもよくなった。
今回使った吸音材だが、確かに羊毛という自然素材からくるのか、貼る場所による変化も明確に出ており吸音材としてよく効いているのだと思う。
自然素材だと言って優しい音をイメージしがちだが、意外と元気な音が出ている。
気のせいかアンプのボリュームは一定にしてテストしていたのだが、音量がアップして聴こえる。
◆その後、システムが変わると吸音材も変わる?
上記の背面2枚重ねでスーパースワンは落ち着いたかと思った。
しかし、もう一組のメインスピーカーであるaudio pro FS-20 を改造、さらにパソコンとDACをUSB接続から同軸デジタルに変換して同軸ケーブルを吟味、スーパースワンにスーパーツィーターキットを追加するなどシステムは日々進化(変化)していく。
するとaudio pro FS-20 に比べてスーパースワンが聴き劣りするようになってきた。
これではイカン!と改めてスピーカーケーブルを交換したりしてみたが満足がいかない。
それで、もう一度吸音材の貼り方をいろいろ変えてみた。
結果、背面の2枚を1枚にして、貼っていなかった天板に薄くした1枚と側面にも薄くして吸音材を貼ったところスーパースワンがよみがえった!
(※ここまで良くなるとは思わなかったので写真を撮っていなかった)
吸音材は癖をとることに専念するがあまり大事な音も失ってしまうことがある。
特に小型スピーカーの場合はフルレンジやそれに近いウーファーが使われることがあり、吸音しすぎるとエンクロージャー内の空気の密度が上がったようになりスピーカーのユニット動きが鈍くなる。
いくらウール吸音材 DCP-A001のような良いものを使っても、量や貼り方がまずいと効果が発揮できない。
吸音材は素材も大事だが、適量を適所に貼る事が重要だとつくづく思う。
その点、最近のメーカー品はコンピュータ解析して適量適所に吸音材を貼って測定しながら作っている。
自作スピーカーマニアでそこまで出来る環境やノウハウがある方は珍しい。
オーディオマニアでも、私のように手探りで何度もテストを繰り返している方が多いと思う。
そのような場合はメインスピーカーを2組使って比較すると軌道修正が図れるのでお勧めだ。

スーパースワンとは
20年以上前からの付き合いであるスーパースワン 。
オーディオ評論家の長岡鉄男氏の設計したスピーカーの中で、最も傑作のスピーカーの一つ。
実はスーパースワンの前身は、スワン と言うスピーカーで、フォステクス FE108シグマと言うユニットを使って設計している。
スピーカーは点音源が理想的とした場合、小型にすると低音が出ない。
そこでユニットの裏側から出る音を活かして、低音を増幅するという発想のもと設計されている。
氏はそれ以前、バックロードホーンは20cmや16cmのフルレンジで設計しているがいずれも大型でかつスーパーツイーターを追加して使うものだった。
スワンは10cmフルレンジ一発で高音から低音までしかも点音源でという挑戦のもとできた傑作スピーカー。
スワンというネーミングは、水鳥の白鳥のこと。
ユニットが設置されていヘッド部分、これはバックロードホーンでいえば空気室とう。
ユニットの裏側から空気室に放たれた音は、スロートといい、白鳥でいうと首の部分を通って胴体部分に達する。
胴体部分の中は、迷路のようになっており末端の開口部に向かうに従って、音の通り道が広がっていく。
この構造により音が拡大される。
トランペットなどホーン楽器は、音の出る開口部のベルに向かって徐々に菅が太くなっている。
バックロードホーンスピーカーはス低音を伸ばそうとするとホーンの距離が必要で、ペース的に2〜3mものホーンをスピーカーにまっすぐに付けるわけにいかないので、実用上ホーン部分を折り返しながら広がっていく工夫がなされている。
ホーンが何回か折り返されているうちに高音も減衰する。
ホーン開口部からは低音がでて、空気室いわゆる白鳥の顔の部分であるヘッドに取り付けたユニットの音と合わせてて耳に届くこととなる。
長岡鉄男氏はこれを夢で見て設計を思いついたと言うのだから、いつもスピーカーについてアイデアを考えていた事がよく分かる。
スワンからスーパースワンへ
スワン以降、フォステクス のFE108superと言うバックロードホーンスピーカーに特化したユニットが出るのだか、そのユニットが超強力磁気回路な為に専用のスワンの設計がなされた。
それで出来たのがスーパースワンだ。
スーパースワン のユニットはフォステクス から出ているFE108シリーズの限定モデルだが、FE108super⇒FE108ES⇒FE108 ESⅡそして FE108sol と販売されてきた。
過去のフォステクスのFE108系統のユニットは、たまにヤフオク!などで見かけることがあるので、興味のある方は覗いてみて欲しい。
現行のスタンダードユニットでは、フォステクス FE108E-シグマが使える強力ユニットだが、FE108superのような超が付くほどの強力なユニットではないので、スーパースワンよりスワンaや方向性を変えて箱型のバックロードホーンのエンクロージャーを自作するか、買うほうが FE108E Σには良いかもしれない。
確か長岡鉄男氏はESが出た後にお亡くなりになっているので、FE108ES2 やFE108solについては当然だが、長岡鉄男氏による専用スーパースワンの箱は設計されていない。
他の自作マニアの方が、ユニットの特性を活かして設計を見直しされているが、私はユニットを変えても箱はスーパースワン のままだ。
確かに新しく開発されたユニットは以前には無い良さが有るが、スーパースワンはFE108super用に設計された箱なので、相性はやはりFE108superが一番だとは思うが、FE108solやFE108ss-HPでも実力は十分発揮されると思う。
スーパースワンの設計図はオントモ・ムック/こんなスピーカー見たことない! (ONTOMO MOOK AUDIO)にも記載されている。
スーパースワンの使いこなし
私は歴代のFE108シリーズ限定ユニットが出るたびにスーパースワンに使ってきており現在FE108solが付いている。
ケーブルの交換や鉛粒やジルコンサンドや吸音材の調整やインシュレーター、塗装仕上げと色々改善してきた。
👇もくじをタップすると読み返したい箇所にジャンプします。
【もくじ】
✅\Amazon ポイントのチャージをお忘れなく!/
2021年9月20日更新
2020年2月3日