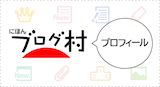仕上げをしていないスピーカーなんてもったいない! 塗れば分かる音の良さ!
"素材の味を活かす"
"何も足さない、何も引かない"
いい言葉だと思うが、それが全てでもないのも事実である。
そう言い切れるのは、シナ合板で作りっぱなしの自作スピーカーを20年を経て塗装仕上げし、初めてその高音質ぶりにショックを受けたからに他ならない。

【もくじ】
組み立てて終わりの自作スピーカーたち
日曜大工でスピーカーを作成するのが楽しかった。
月刊誌のStereoで6月号といえばオーディオ評論家の長岡鉄男氏設計の新作スピーカーが掲載されるので、毎年この時期はわくわくしながら本屋に予約して購読していた。
氏は誰にでもわかりやすく板取図のカットするパーツごとに①②、、⑳など番号を振り、その番号の順番通り組み立てると楽にスピーカーが組み立てられる設計図を掲載していた。
スピーカーに使う板も、一般的にホームセンターなどで手に入るベニヤやシナ合板を使っている。
板取もできるだけ無駄のないように考えられ、それを一つの制約として設計されており尽きることのないアイデアに魅了された。
長岡鉄男氏のスピーカー工作の記事は、基本的には組み立ててから、ユニットやネットワークを付けて配線し、視聴レビューするというもので、仕上げの工程は無かった。
当時はバックロードホーンなど氏の設計をもとに読者が作成されたスピーカーを雑誌に写真が掲載されているページを見ると、ほとんどが作りっぱなしの仕上げられていないものだった。
長岡鉄男氏は仕上げをすることによるメリットについては何度も説明されており、それは読者に委ねているというスタンスだった。
我々ファンは早く作って音を聴きたいという欲求が先立ち、すぐに音を出してしまう。
しばらくエージング(ボンドが乾く、木の歪が落ち着く)してから仕上げようと思うが、なかなか手が回らないというのが実情か?
実際に私もスーパースワンなどシナ合板で自作してから2017年まで仕上げをしていなかった。
いつ仕上げをやろうか、、、と思っているうちに、かれこれ20年が経ってしまっていた。
ダイノックシートで仕上げたスピーカー
テレビ用のMX−20AV とAV1ーmk2はダイノックシート貼りで仕上げて、細かい部分はさておき概ね満足している。
仕上げ前や工程の写真はないが、ダイノックシートは大きなシールのようなもので、作業中にペタペタとひっついて苦労する。
建築の内装業者でも、壁のビニルクロスや床のクッションフロアーは貼ることができても、ダイノックシートは貼ってくれない職人さんが多い。
ダイノックシートは、ダイノックシート貼り専門の職人さんがいるくらいで、とても貼るのが難しい。
昔、仕事の関係でクロス貼りの内装の職人さんと話をしていたが、「ダイノックシートだけはやりたくない。」と言っていた。
仕上げにこだわるダイノックシート貼りのプロの職人さんでも、失敗すると剥がして貼り直すことができない箇所は、また新しいダイノックシートを使ってやり直すことになる。
また、ダイノックシートを貼る前にも下地処理をしっかり行わないと気泡ができたり浮いてきたりする。
でも、ダイノックシートは単色のものだけでなく、艶あり、艶なし、木目調、大理石調など種類がたくさんあり、ビルやマンションのエントランスや店舗の改装などでダイノックシート使用すると見違えるようになる。
ベニヤ板のスピーカーもダイノックシートを貼ると、どこにも売っていないオリジナリティーのあるスピーカーへと変身する。
見た目が良くなると音質的にも良い効果が表れてくる。
テレビ用スピーカーMX-20AVの仕上げ
リビングのテレビ台とテレビに挟まれているフルレンジユニットが3つのスピーカーも長岡鉄男氏設計。
その型番はMX-20AVというもので、これ一台で、普通のプリメインアンプでサラウンドが実現出来る。
同じ仕組みのスピーカーが音工房Zから発売されている。
これで初めて聴く人は横や後ろにスピーカーがないか?とキョロキョロする。
MX-20は、組み立てる前にカットした板にダイノックシートを貼ったので、特に苦労しなかった。
組み立てる前にシートを貼ることが、きれいに仕上がるポイントかもしれない。
尚、木口の部分はうまくシートが貼れなかったので東急ハンズで物色し、薄い長細いオイルステインで仕上がっている15mm幅の棒を貼りつけている。

リビングはオーディオマニアではない家族も一緒に過ごす場所。
ベニヤ板時代のMX-20を知っている近所の身内が家に来て、ダイノックシートで仕上げたスピーカーを見たときには驚いていた。
逆に言うと、ベニヤ板の仕上げていないスピーカーを見てどう思っていたのかが想像できる。
テレビ台兼用バックロードホーンスピーカーAV1-mk2の仕上げ
これは実家にいるときに作ったもので、独立後寝室にテレビを置きたくなって、実家から運んできたテレビ台兼用のスピーカー。

というより家具?
結婚して独立したときも、まだシナ合板がむき出しのまま仕上げをしていなかった。
スピーカーヘッドと台の表面と棚とで合計4種類のダイノックシートを使った。
これはすでに組み立て済みだったので、入り組んだところやシートを巻き込まないといけない箇所が多々ありダイノックシートを貼るのに結構苦労した。
しかし、ダイノックシートで仕上げると見違えるようになり部屋とよく馴染み、圧迫感がかなり減った。
特に貼る面積が広いためか、ダイノックシートを貼ると共振が抑えられ音質もSN比がよくなった。
もともとは25インチのブラウン管テレビ用として長岡鉄男氏が設計したものだが、氏も母屋の和室のコーナーでこれのもとになるAV-1を使っておられた写真を見たが、仕上げはされていなかったと思う。
仕上げをして最新ユニットに入れ替えたAV−1MK2の音の良さを設計者の長岡鉄男氏にも視聴して貰いたいぐらい良い音に生まれ変わっている。
塗装で仕上げたスーパースワン
2017年の暑い夏の日、重い腰を上げてようやくスーパースワンの仕上げをすることになった。
スーパースワンは形が単純な四角ではなく特にヘッド部分は面取りをしているので曲面があり、私の技術ではダイノックシートは無理と判断した。
ダイノックシートは様々な柄があり、いい柄を選ぶと確実に高級感が増すのでおすすめだが、継ぎ目や折り目をどのようにするかが難しいし、巻きこんだ木口の処理がさらにやっかいですぐにめくれてくる。
塗装をすることにした。
塗料も色々あり、家の中で作業するので匂いの出ない水性塗料にすることに決めた。
ただ単色でベタ塗りをしてもあまり面白みは無いので、質感を出すために水性ウレタンニスを採用した。
ツートンカラーにしたかったので、主にマホガニーとブラックを使った。
下の写真はまだブログを始めていなかったときで、細かい工程を撮影できていないが雰囲気だけでも感じていただければと思う。
(仕上げなしのスーパースワン)

①紙やすり、耐水紙やすりで、スピーカーの表面、塗装した表面を研磨する。
(#240⇒#320⇒#800⇒#1000⇒#1500などの順番に!)
②水性ウレタンニスを刷毛で均一に塗る。
(*色を変える箇所はマスキングテープでカバーする。)
この①②の繰り返しを私の場合は5回ほど行ったと思う。

単純作業だが、回を重ねるごとに色に深みと艶が出てきて、気になっていた工作の精度の悪さなんか目につかなくなる。(2m離れれば、、だが?)
紙やすりは回を重ねるごとに目の細かいものを使う。
前半はヤスリでゴシゴシこする感じだが、後半になると磨くという感覚に変わってくる。
水性ニスは見本の色などがあるが、塗り重ねると、どんどん濃くなるのであくまでも参考程度にするとよい。
狙った色を出すのは素人ではとうてい無理なので、結果オーライで割り切る気持ちが大切だ。

塗装が乾いてスピーカーユニットを取り付けると本当に見違えるようになる。
2,3日は、我ながらよくやったと仕上がったスピーカーに見惚れていた。

MDFのスピーカーの塗装は下地処理に要注意!
私の自作したスーパースワンはシナ合板に直接水性ウレタンニスで塗装したが、もしMDFでエンクロージャーを作成している場合は塗装仕上げをするときは注意が必要だ。
MDFは「medium-density fiberboard」の略で、日本語では中密度繊維板というらしく、
木材チップを蒸煮したり、解繊したものに合成樹脂を接着剤として混ぜて熱して板状に加圧形成したもの。
このMDFに塗料を直接塗ると塗料の吸い込みが激しく上手く仕上げができない。
吸い込みにより、なかなか色が乗らなかったり、ムラになったりするので塗装仕上げをする前に「シーラー」という下地材を塗っておく必要がある。
なお、MDFは普通の合板よりも密度が高くかつ加工がしやすいので、メーカー製のスピーカーのエンクロージャーにも使用されていたりする。
メーカー製のスピーカーは、MDFの上に突板や塩ビシート仕上げが施されている。
音工房Zのスーパーツイーターキットを塗装仕上げしてみた!
10cmフルレンジ一発のスーパースワンの超高域をグレードアップするべく音工房Zの
スーパーツィーターキット(ペア)を追加してみた。
もし、気に入らなければ手持ちの他のスピーカーに回そうと思ったが、非常に好感触だったので、スーパースワンに音工房Zのスーパーツィーターキットをそのまま採用することにした。
このままでは、見た目にとってつけた感があるので、スーパースワン本体と同色で塗装仕上げをする。

ちなみに、音工房Zのスーパーツィーターキットは、MDFのケースとリボンツイーターと1μFのフィルムコンデンサと木ねじがセットとなっている。
フィルムコンデンサの容量で音のバランスや音質全体が変わるので、同じSolenというメーカーのフィルムコンデンサを購入し容量を調整しながら楽しんでいる。
音工房Zのスーパーツィーターキットはユニットを嵌めるケースがMDFを加工して作られているようだ。
これを「シーラー」とスーパースワンと同色のマホガニーの「水性ウレタンニス」で仕上げた。

下塗りで使用するのは水性のサイディングシーラー

まずMDFのツイーターのケースを紙やすりで整えておく。
紙やすりは#240、#300、#400、、、、、#1500など数値が大きくなるほど目が細かくなる。
最初は目の粗い紙やすり(#240くらいか?)でMDFの表面の毛羽立ちを落としておく。

紙やすりの木の粉を除去してから、水性のサイディングシーラーを塗る。

塗ってから30分から1~2時間乾かす。(気温や湿度による)

しっかりシーラーが乾いたら、最初より少し目の細かい(#300~#400くらいか?)紙やすりで擦る。

「シーラーを塗る→乾かす→紙やすりで擦る」を2~3回繰り返す。
最後は#1000くらいの紙やすりで磨いておく。

仕上げは水性ウレタンニスで仕上げていく。

捨てても良いような容器に、塗料を重ね塗りするたびに注ぎ足していく。

下地用シーラーを塗っているので色の乗りが最初から良い感じになる。

塗料を吸わなくなっているので塗ってから2時間から半日くらいは乾かす。
そして紙やすりを掛ける。(#400~#1000~#1500くらいか?)
これを数回(できれば3回以上、自分が納得するまで)繰り替えす。
※ここは焦らず気長に作業する。

私は無理やりドライヤーやサーキューレーターで乾かしたので、5回くらい塗っては乾かしてやすり掛けを繰り返した。
すると写真のように鏡面仕上げのようになる。(内側の細かい部分は塗料が溜まりやすく乾かないうちにやすり掛けをすると塗膜がめくれてしまう。)

あとは結線しておいたスーパーツイーター本体を塗装仕上げをしたケースに木ねじで取り付けるだけ。

自分自身はかなり綺麗に仕上がったと思っているが、塗装マニアやペイントの職人さんがみるとどうかな??

スーパースワン本体と同色の水性ウレタンニスで塗ったので一体感がある。
なるべく販売されている色をほかの色と混ぜずに、そのまま使うと後々に色合わせに困らなくて済む。

塗装仕上げをすると見た目と音に磨きがかかる
最新の限定ユニットFE108SS-HP【飛びねこ工房】のダブルバスレフエンクロージャーを購入してみた。パインの集成材で無塗装でもきれいだがそのままにしていても日焼けや汚れが付いてくるので水性ウレタンニスで仕上げてみた。
好みの色になるまで10回くらいは塗り重ねたがコテバケ のおかげで意外と早く2日間で仕上がった。
やはり期待通り音の質感が著しく向上した。

パイン材の無塗装でも美しい飛びねこ工房のスピーカーだったが、そのままでは汚れや日焼けをするので塗装することにした。

|
スピーカー工房 飛びねこ
|
塗装をする際に大変重宝したのがコテバケだ。

普通のハケで塗装するよりもハケムラができにくく、作業効率も大変良いので塗装の初心者にこそ大変おすすめだ。

余談だが、ウォールナット色の水性ウレタンニスが余ったので、後日PC用のデスクにしているテーブルをコテバケを使って塗装してみた。
スピーカーより幅の広いテーブルでもワンタッチコテバケ は大活躍だった!
あまりにも作業効率が高く、朝から夕方まで乾燥を含めて5回塗りしてもちょうどよい疲労感で大満足のPCデスクに生まれ変わった。
※古いリビングテーブルのおさがりをPCデスクにしていたが、コーティングも剥げており、ホコリが積もりやすく手触りが悪かった。
ハンディクラウン ワンタッチコテバケ INNOVA 1395200200 150mm
コテバケで水性ウレタンニスを綺麗に塗れてしまう。
「塗って、乾かして、軽くやすり掛け」を5回繰り返した。

落ち着いた艶消しのウォールナットのPCデスクに生まれ変わって大満足!

試しに以前に塗装したスーパースワンにコテバケを使って水性ウレタンニスの艶ありブラックを重ね塗りをしてみたところ前のハケムラが目立たなくなり、かなり深みと艶が増して手触りも良くなった。

艶ありの水性ウレタンニスで塗装仕上げをしたスピーカーにランプ(照明)を近寄せると、ランプが映るぐらいツルツルな鏡面仕上げになる!

十分乾燥させてスーパースワンから音出しをした瞬間、
「いったい20年間何を聴いていたのだろうか?!」
と思うほど音質が見違えるように向上したのには驚いた!!
これは全く別物のスピーカーであり、大袈裟ではなくグレードが倍以上もランクアップした!
静けさが増し、低音〜高音までレンジが広がり、細かい音や響きも再現されダイナミックレンジも格段に良くなった!
自作スピーカーを仕上げていない方は、騙されたと思って水性ウレタンニスなどで塗装仕上げやダイノックシートを使って仕上げをする事にぜひチャレンジしてみて欲しい。
きっと、お蔵入りになりかけていた自作スピーカーも化粧をしてあげれば、ルックスも音も惚れ直すことは間違いない!!

👇もくじをタップすると読み返したい箇所にジャンプします。
【もくじ】
◆Amazon Music unlimitedに加入して高音質で音楽を楽しもう。
自宅でも、外出先でも、簡単に音楽にアクセス
追加料金なしでHDが利用可能に!
\Amazon Musicの詳細はこちら/
クリック!👉✅https://amzn.to/3aq5qSF
◆Audible会員は定額で12万以上の対象作品が聴き放題で楽しめます。
\30日間無料体験はこちらから/
タップしてください👉✅https://amzn.to/3mfTrdg
2021年9月23日更新
2020年1月13日初回投稿












![【国内正規品】[SFC12]Solen FastCap (0.82μF:630V)「2個セット」 FASTCAP630V0.82 【国内正規品】[SFC12]Solen FastCap (0.82μF:630V)「2個セット」 FASTCAP630V0.82](https://m.media-amazon.com/images/I/41jq-W7vIuL._SL500_.jpg)