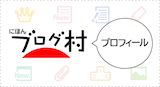床置きでも高音質でブックシェルフ スピーカーを鳴らしたい!

【もくじ】
床に座って、床に置くシンプルスタイル
「床に座る」畳は日本の文化
四畳半は茶室の基本形と言われている。
畳の床に座って、茶をもてなすという文化である。
茶道では畳の床に茶碗を置く。
お湯は畳の下に仕込んである「炉」(ろ)で沸かす。
私の祖父母の家に、昔は囲炉裏(いろり)があった。
遠い昔の記憶だが、囲炉裏で湯を沸かしたり、魚を焼いたりした記憶が薄っすらと残っている。
昔は、床に御膳を置き、食事をしていた。
そんな田舎の家も、いつしか囲炉裏は無くなり、掘りごたつに変わった。
冬の田舎の家は寒さが半端ではなく、掘りごたつに足を入れるとそこから動けなくなる。
今でも残っている床で暮らす習慣
マンションでも洋間やフローリングのリビングにもかかわらず「広さは何帖あるの?」などと聞かれる。
マンションの広告でも、”洋間6.3帖” などと畳を想定した表現がされている。
畳のないワンルームマンションでも、玄関で靴を脱ぎ部屋に入る。
これも床に座る文化の名残だと思う。
シンプルに暮らす人たち
ミニマリストという生活スタイルを送る人がいる。
物を持たない事に徹している人たちことだが、私などはその対極にいる人間だと思う。
狭い部屋に、所狭しとオーディオやテレビや家具家電に囲まれる生活を送っている。
ミニマリストから見れば、眉をひそめられそうな部屋である。
オーディオマニアは、リスニングチェアやソファーなどに座って音楽を聴くことが多い。
しかしミニマリストまでと言わずとも、ベッドや椅子やソファーを置かずに、目線より低い家具を置くなどしてシンプルに床に座って過ごす生活スタイルもある。
床に座って音楽を聴くスタイル
「ソファーより座椅子に座って生活している。」
「目線より高い位置に物を置きたくない!」
「床に座っても高音質で音楽を聴きたい!」
お気持ちは、よ〜くわかる。
私も中学から高校に入るまでは、リスニングチェアなど無くて床に座って音楽を聴いていた。
そんな床で過ごす方へできるだけ高音質で音楽を鳴らすための提案をさせていただくこととしよう。
床に直置きするオーディオの問題点
ブックシェルフ型スピーカーを床置きすると音が篭る。
ブックシェルフ型のスピーカーを部屋の床にそのまま直に置くと、低音が床に反射することにより中高音がマスクされる。
いわゆる低音がかぶってしまっている状態になる。
更にスピーカーの振動がもろに床に伝わり、床が共振して音が濁ったり、床の振動がアンプやプレーヤーまで伝わることで音が濁り解像度の悪い篭った音になってしまう。
「ブックシェルフ型スピーカーの床置きは、スピーカーを50〜60cm床から浮かせて、、、、。」
など、と言いたいところだが、これでは床で聴く対処方法にはならない。
床で聴くシンプルなライフスタイルでは、出来るだけスピーカーは目線より上にあると圧迫感が気になる。
床にスピーカーを直置きする際のポイント
床置きでも出来るだけ高音質で鳴らすポイントは
スピーカーを後ろに傾けてセッティングする事!

2way以上のブックシェルフスピーカーであれば、ツイーターが耳の位置を指すようにスピーカーを後ろに傾けてみる。
1980年代にヤマハからNS-05という床置き専用のスピーカーが発売されて話題になったことがある。
このヤマハのNS-05は、傾けてセットできるように専用のスタンドが付いていた。
【YAMAHA NS-05】

最近のデスクトップスピーカーでは、傾いているものが発売されいるがそんなイメージである。
中型スピーカーなど少々背の高いスピーカーの場合は、更に傾けてツイーターから出た高音が頭上を指すようになっても構わない。
これは低音のかぶりを減らす事を優先させる為である。
ただし、スピーカーが倒れると危険なので、傾きはスピーカーの前後の重心を考慮する必要がある。
更に部屋を広く使うためにスピーカーを壁に寄せたい場合があると思う。
”壁から離して、、、”
と言いたいところだが、スピーカーが前にせり出してくると圧迫感がある。
壁にスピーカーを寄せたい場合は、壁の頑丈な場合を探して(手で壁をノックするように叩き、空洞に鳴っていない下地が有るところを探る)スピーカーをその丈夫な壁にもたれさせるよう傾けてみるのも方法のひとつ。
壁とスピーカーの接触する箇所はガタツキやビリつきはが無いようフェルトやブチルゴムなどを挟んでおくと良い。
下の写真はブチルゴムテープを3層重ねにしてサランラップで巻いている。

床が畳の場合でも壁のほうが丈夫であれば、丈夫な壁を使ったセッティングの方が音質が良い場合がある。
床が畳と違ってフローリングやクッションフロアーなどの場合は、床下に根太が組まれているところを手探りで壁と同じ要領で叩いて探しだし出来るだけ丈夫な位置をさがす。
できれば御影石や人工大理石などでしっかりベースを固めて振動対策をしておいた方が良い。
スピーカーの傾け方(仰角セッティング)
スピーカーの傾け方だが、角材やブロックやレンガなど出来るだけ丈夫で重たく硬いものをスピーカー正面側の底板に噛ますとよい。

高さ調整をインシュレーターでする場合は、スパイクや円錐形のものを薄い両面テープで貼り付けると良い。
【インシュレーター】
【ブロック、レンガ】
スピーカーはコーナーを避けて設置することが重要!
スピーカーの後ろの壁と床が近いだけでも低音が増強されがちなので、出来るだけ低音のかぶりを避けるため、スピーカーを部屋の隅に押し込まないような配置にすることが重要。
その他の方法
アンプのBassツマミがあれば絞る。(低音を小さくする。)
グラフィック・イコライザーを使ってみる。
アンプのBassツマミで低音を減らすよりも、特定の周波数を細かく調整できる。
ただし意外と使いこなしが慣れるまで難しい。
[rakuten:book:20027919:detail]
バスレフポートを塞ぐ。(ダンプドバスレフ)
バスレフタイプのスピーカーの場合は、バスレフポートに脱脂綿や吸音材、スポンジなどを適当な大きさに切って塞いでみると良い。(低音の量感が減る。)
バスレスポートをふさぐと密閉型スピーカーの特性に近づき、低音の量は減るが最低周波数は逆に伸びる。
スピーカーによっては、下の写真のようにバスレフポートを塞ぐ為のスポンジが付属している。

低音が引き締り、中高音がくっきりするスピーカーケーブルを選ぶ
カナレであれば 4S8 よりも4S6 、さらに高音域を強調するには無酸素銅の4S6G が効果的かもしれない。
その他、選び方としてはスピーカーケーブルは、太さだけでなく手触りと音の傾向が似ており、固いケーブルはカチッと締まった音で、柔らかいケーブルはふくよかな優しい音がする傾向にある。
床置きの影響の少ないスピーカー選び
【YAMAHA NS-05】

昔、ヤマハが発売していたNS-05が床置きを想定して設計されたスピーカーがあった。
低音のかぶりを想定してウーファーの口径が10cm位の小型でスリムなものだった。
仰角セッティング出来るようなスタンドになっていた。
それに近い形がJBL L100 Classic ブックシェルフ スピーカー
さすがにアメリカのJBLなので、これは床置きというよりソファーに座ってゆったりと音楽に浸る感じだと思う。
スピーカーを壁に近づける場合、なるべくバスレフポートが正面に設けてあるほうが良い。
最近では、バスレフホートが下向きなっており低音が後方だけでなく360度に放射するタイプもあるようだ。
[rakuten:audiounion:10052186:detail]
ブックシェルフスピーカーを床に直置きしたい場合は、出来るだけ低音が特定の周波数でブーストしていないものが良い。
スピーカーの方式としては、バスレフ型で特定の周波数の低音を増強しているものよりの密閉型スピーカーのほうが低音に膨らみが少ない。
クリプトン 2ウェイ密閉型スピーカーシステム(ペア) KX-05II
以上、スピーカーを床に直置きする事を前提としてセッテング方法を説明したが、スピーカーを傾けて設置できるタイプのスピーカースタンドも販売されている。
椅子に座っても、目線よりスピーカーを低く設置する場合にもおすすめ。
【専用スタンド/JS120BLK付】JBL L100 Classic/ORG オレンジ ペア ブックシェルフ スピーカー
最後に
オーディオマニアとしては、もっと徹底的に床の振動対策を行なって欲しいところだが、床で聴くシンプルスタイルどころでは無くなってしまう。
床の振動は音量に比例するので、部屋をシンプルに保ちたいのであれば、小音量で鳴らさざるおえない。
小音量でも高音質で鳴らす場合には、なるべく能率の高い反応の良い軽い振動板を使ったスピーカーを選ぶ方が鳴らしやすい。
また、スピーカーユニットがスピーカーボックスの上の方に取り付けているタイプのものが床からの反射を受けにくいので下の記事を参考にしていただければと思う。
👇あわせて読みたいリビングオーディオのおすすめ記事
2022年5月2日 更新
2020年3月3日(初回投稿)














![F500 [BO:ブラックオーク] FYNE AUDIO [ファインオーディオ] ペア ブックシェルフスピーカー FYNEAUDIO F500 [BO:ブラックオーク] FYNE AUDIO [ファインオーディオ] ペア ブックシェルフスピーカー FYNEAUDIO](https://thumbnail.image.rakuten.co.jp/@0_mall/avac/cabinet/imgrc0095294873.jpg?_ex=128x128)







![オーディオアクセサリー大全 2024~2025 (2023-07-26) [雑誌] オーディオアクセサリー大全 2024~2025 (2023-07-26) [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/51thg2dmFQL._SL500_.jpg)