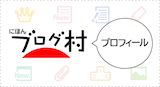◆スポーツでも、楽器の演奏でも基礎が大事で。
基礎練習をしっかりした上でテクニックや表現力を磨くのである。
建築でも基礎工事で手抜きがあると家が傾いてくる。
今日はオーディオにおける基礎の話しをしてみたいと思う。
音というのは、振動である。
その振動を発するのはオーディオシステムのスピーカーの役割。
スピーカーユニットは簡単にいうと、マグネットの中にコイルが仕込まれておりそのコイル(ボイスコイルという)に電流が流れると前後に動きその事によって振動板(コーン紙、ダイヤフラム)が振動をして空気を動かし音となって耳の伝わってくる。
振動板はダンパーやエッジを介してユニットのフレームに固定されており、そのフレームはスピーカーのエンクロージャー(スピーカーキャビネット)に固定してされている。
振動板はユニットのフレームを通じてエンクロージャーに固定され、そのエンクロージャーをスピーカースタンドなどを介して部屋の床面に固定されているのである。
スピーカーユニットの振動をしっかり受け止めロスなく音にするためには、エンクロージャーが振動によって動かず、それを支えるスタンドや設置する床面がしっかりとしていないと行けない。
いわゆる土台がしっかりしている必要がある。
建築でいう基礎である。
建築の基礎はコンクリートや石などしっかり重く硬いもので作られ建物を支えている。
土地の地盤が柔らかい場合は硬い層まで杭を打ってしっかり固定する必要がある。
スピーカーも床面にしっかりと支えられていることが重要!
床面が和室場合には畳が敷いてあり、洋間でも厚いカーペットが敷いてある上にスピーカーをそのまま置くとふらついてしまう。
更にスピーカースタンドで高さを稼ぐと床から高い方ほど揺れが大きくなる。
ふらつかないようにするには、しっかりした土台が重要なのである。
欧米などは床面にカーペットが敷いている場合は、スピーカースタンドの下から床に向かってスパイク出ておりカーペットを貫通してカーペットの下の石やコンクリートでできた強固な床に建築の基礎の杭のようしっかりと固定させている。
現在ではスパイクのあるスピーカーは珍しくないが、昔から特にヨーロッパの小型スピーカーのスタンドは鋭く尖ったのスパイクが備わっていた。
そのうち日本でも確かオーディオテクニカだったと思うが、畳を貫通するほどの長いスパイクが付いているインシュレーターが発売された。
これは畳の下の床材までしっかり固定するものである。
現在では貫通するためどころか、スパイク受けなど床面に傷がつかないように配慮されている。本来のスパイクの役割とは違った使い方となっている。
昔、ティップトゥ(STAXと言うメーカーだったと思うが忘れた。)と言うものが最初だったと記憶しているが、円錐状のインシュレーターが販売されるようなり人気の商品となった。
これは上記の貫通すると言うことを狙ったというより、点で支えることにより床面に振動を伝えない用にするのが主な目的である。
現在でもその流れを組むものが販売され、スピーカースタンドや家具や床面を傷つかないようにスパイク受けというものとセット売りされていることが多い。
日本のマンションなどの場合、鉄筋コンクリートの床スラブの上に角材を一定の間隔で並べて固定し、さらにその上に12mmや24mmのベニヤ板などを貼り、その上をカーペットやフローリング、クッションフロア、長尺シートやタイル、畳など化粧材が貼られているのである。
欧米の石造りの家などの床と比べて、一般的に日本の住宅の床はオーディオにとってあまり理想的ではないことが多いのではないであろうか?
大げさな表現ではあるが、”床を制するものはオーディオを制する!”という言葉を過去にあるオーディオ評論家の方が言われていたことがある。
強固な床面の部屋をお持ちの方は大変羨ましい限りである。
私などは和室の畳敷のため、土台作りから始めないとならない。
一度、床面を剥がして角材の間隔を狭めたりして補強し、厚い板に張り替えようかと考えた事もあったがかなり大掛かりとなるため断念した。
そこで方法としては、スピーカーを設置する床面にできるだけ重くてしっかりしたある程度面積の広い板を敷き基礎を設けてやることである。
ホームセンターなどで手に入るものとしては、24mmベニヤなどできるだけ重たくしっかりした厚みのを900mm×900mmや900mm×600mmや600mm×450mmなどにカットしてスピーカー(又はスピーカースタンド)の下に敷くのが良い。
もっと重たいものはコンクリートの板や御影石などの板である。
私は、今では一人では運べないほどの重たいコンクリートの溝の蓋をホームセンターで購入し表面を化粧したものを若い頃に作成し、今でもメインシステムのスピーカーの下に土台(いわゆる基礎)として使用している。
御影石の板はリビングのサブウーファーの下に設置している。
このサブウーファーは25cmのユニットで、バスレフポートが真下(エンクロージャーの底面)についてあり、もろに床に振動を伝えるためポンと床に置いただけでは部屋中の床壁天井、家具が振動してしまい余計な音が発生してしまう。
御影石は30mm厚だがスペースの関係でサブウーファーのキャビネットと同じくらいの面積しかない大きさにも関わらず、これでも有るのと無いのとでは随分違う。
このようにコンクリート板やベニヤ板、御影石の板などにしっかりとスピーカーをがたつきなく設置することで床、壁、天井、建具や家具など振動がで伝わらないようなり、スピーカー本体をしっかりと支えることができてロスが少なくなり音質の向上が見込まれる。
ローボードや本棚など家具の上に設置している場合でも強化ガラス板や人工大理石などで土台をしかりと固めてやることによってスピーカー本来の音が出るようになる。
基礎が大切であり、その上でインシュレーターなどを併用し振動を制御して自分の音を好みに近づけることができる。
オーディオアクセサリー類を使ってもなかなか音の変化が感じられない場合や定位がしかりせず音が視えない場合など悩まれているかたは、もう一度基礎を見直してはいかがだろうか?
2019年12月1日